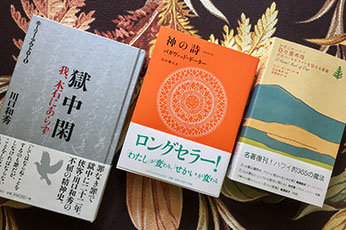MAGAZINEマガジン
青山堂運歩 by 川島陽一
意識の目と骨法
『頸部前彎療法』=『調律』において姿勢を見ることの大切さを生徒さんに強調することがある。身体という存在の表面的形態や様相の底に伏在する、根源的な構造を直視するということ、それはいわゆる骨法と呼ばれる古来、東洋の芸術論や画論に見られる、見る働きの深化、つまり、見る働きを深める、深化させるということに意識の目を向けるということが必要とされるとおもうからである。
今、意識の目、と表現したが、われわれの意識の構造における深層的意味領域、フロイトやユングの深層心理学の研究の精華を通じて、人間の意識の社会生活的表面の底に下意識的な薄暗がりの領域を想定し、通常は気づかれない形で、浮動し、流動していく意識の星雲のようなものへ目を向けるということ。人間の日常的、常識的意識上に設定されているところの、意識せぬ言葉にも、その使い方次第では、普通の人間の使う普通の言葉にほかならないとしても、実体は底知れぬものが隠され、秘められているということをわたしたちは知る。
フロイトが『夢解釈』の中で、秘密のエクリチュール、と語るもの、かれは無言の、古代エジプトの象形文字に見られるような物言わぬ記念碑、沈黙のしるしピラミッドに着目する。大文字のAは、その大文字性においてピラミッド性を示す。かつてヘーゲルは、古代エジプトの王者の墓、ピラミッドに大文字記号Aの外体をなぞらえた。それこそは、ヘーゲルの骨法といえようか。
カイロプラクティックの根本の考え方、被験者の首の上部のあたり、頭頂部の下の違和とは、ヨガのチャクラ、カッバーラーのセフィーロートを連想させる。それはヘーゲルの神秘主義にも通じるユダヤ神秘主義カッバーラー文字象徴論なのであった。
荘子も夢空間を語る、「いつか、私、荘周は蝶になった夢を見た。喜々として思いのまま飛び回っており、そのとき確かに私は蝶だった。ただ楽しいばかりでうきうきとして、自分が周であるという意識はなかった。突然眼がさめてみると、なんと、私は周だった。いったい自分は蝶になった夢を見たのか、それとも胡蝶が周になった夢を見ていたのか。どうして私にわかろうか。けれども周と蝶とのあいだには、確かに区別があるのは否みがたい。ほかでもない、この状況をものの変転、物化と呼ぼう。」
道元も夢に見るような話をする、「水の水をみる参学あり水の水を脩証(しょうしょう)するゆへに、水の水を道著(どうじゃ)する参学あり。」訳すと、「水が水を見る見方で、水を見ることを学ぶ、この段階では、「水」を見るのは水であるから、「水」が「水」を語り明かすことになるからである。」(道元「山水経」『正法眼蔵』(二))
ヘラクレイトスはこういう、「ロゴスはこの通りにいつもあるのだけれども、人間どもはこれが分からずに過ぎて行く。これを聞かなかった以前も、これをはじめて聞かされた後もだ。万物の生成はこのロゴスに従って(カタ・トン・ロゴン)いるのだけれども、かれらはその験(しるし)を知らぬ者の如くである。言葉の上でも実際の仕事の上でも、そのような験はあるはずなのに・・・・・」(断片一)
さらに、
「わたしから聞くというのではなくて、むしろロゴスに聞いて、万物が一であることを、ロゴスに合わせて語るところに智というものはあるのだ」(断片五〇)
カイロプラクティック的イネイト・インテリジェンスも、クライアント様に、その験があるはずなのに、その自覚なしにすぎてゆくときもあるわけである。
無意識を個人的なものから集団的なものへと深化させること、そこからなんでも取り出して見せること、一見して何の関係もないような偶然の事実を、フロイトの夢判断などでは、無意識を上手に説明できもする。知性の抑圧をゆるめ、意識の抑圧を外せば、そこには、無意識の底にかくされているものが見えてくるということもありえようか。
三木成夫の『胎児の世界』(中公新書)こそは、無意識の世界の宝庫、宝箱だ。そこには遠いまなざし、という三木の語る、生命の深層、アメーバにまで広がる裾野と生物の山脈に、悠久の進化の時が秘められているのである。総べての生きとし生けるものは胎児の世界の深奥につらなる、いのち、の流れに根差した夢をみている。人類史の根源的な構造を、胎児は見詰めるのだ。
老子『道徳経』第十六章
致虚極 守静篤
萬竝作 吾以觀復
夫物芸芸 各復帰歸其根 歸根曰静
是謂復命 復命日常
極を致し、静篤(せいとく)を守る。
虚万物並びに作り、吾以て復る観る。
夫(そ)れ物芸芸(うんうん)たり、各(おの)おの其の根(こん)に復帰す。
根に帰るを 静と曰う。
是れを命(めい)に復すと謂う。
命に復するを常と曰う。
空虚(からっぽであり、自我がなく、欲望もないこと)の極みを体得し、私は自分自身を、静けさのうちにしっかりと保つ。 万物がすべて一緒に立ち上がってくる。しかし私には、それらが帰ってゆくのが見える。
あらゆるものが旺盛に育つ。しかしそれらは、「根」に帰ってゆくのだ。
「根」に帰ること、それは静けさと呼ばれる。
それは、「天命」へと帰ってゆくということだ。
「天命」へと帰ってゆくということ、それは「常」と呼ばれる。
老子『道徳経』第二十八章
知其雄 守其雄 爲天下
爲天下谿 常徳不離
復帰於嬰児
其の雄(ゆう)を知り、其の雌(し)を守らば、天下の谿(たに)と為る・
天下の谿と為らば、常徳は離れず。
嬰児に復帰す。
雄というものを知りながら、それでも雌の役目を守る。そういう人が、世界全体の峡谷となる。
世界全体の峡谷となるや、「道」の永遠なる「徳」は、かの人から離れることがない。
そしてかの人はふたたび、幼児の状態へともどってゆく。
老子にとって、幼児とは、その本来的な純粋さと単純さゆえに、ありのままなる最も人間としての完全な道、の体現である。三木によれば、胎児は受胎の日から指折り数えて三十日を過ぎてからわずか一週間で、一億年を費やした脊椎動物の上陸説を夢の如くに再現する、という。幼児のなかにある星雲を夢のごとく見て、わたしたちは道、をあゆみつづけ生涯をすごす。
根源的な構造を見ること、骨法の如し。