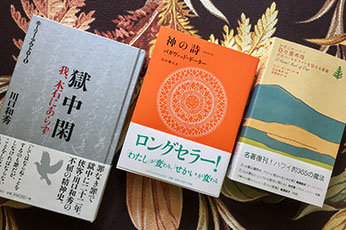MAGAZINEマガジン
本日の一枚
『アート・ホークス(芸術的詐欺師)』?賛否両論だけど、『The Velvet Sundown』の音楽そのものは好きですよ!オレは。
*TAO LABより
このバンド!?の音、聴きました?
Dust on the Wind
The Velvet Sundownについて----AI作品ということで賛否はあるけれど、個人的には好意的に受けとめています。
AIにすべてを委ねるのではなく、人間の感性とAI技術が交差する、その接点にも新たな創造の芽もあるのでは----そんな時代の可能性を感じさせてくれる試みです。
もちろん、全面的に肯定するわけではありません。
けれど、そこに音楽への深い愛情や、人の手ざわりが感じられるのなら、AIもまた創造の一翼を担いうるのでは、と。
The Velvet Sundownには、そんな"融合の兆し"がある気がしていて、そこがとても気になるし、センスも買っています。
現在、バンドのスポークスパーソンで"準メンバー"を名乗るアンドリュー・フレロン(Andrew Frelon)はこう述べてます。
「これはマーケティングだ。トローリング(人々を意図的に挑発して注目を集める行為)なんだよ。以前は誰も僕たちのことなんて気にしちゃいなかった。でも今や、こうしてRolling Stoneと話している。つまり、"それって悪いこと?"って話だよね」
「個人的に、僕はアート・ホークスに興味があるんだ」とフレロンは続ける。「たとえばイギリスのLeeds 13っていうアート学生のグループがいて、彼らは奨学金を使ってビーチで遊んでるような偽の写真を作って、それが大スキャンダルになった。そういうのって、すごく面白いと思うんだよね。今の世界では、偽物のほうが本物よりも大きな影響力を持つことすらある。それってヤバいことだけど、でもそれが僕たちの生きている現実なんだよね。だからこそ、こう思うんだ──そういう現実を無視すべきなのか? リアルとフェイクのあいだ、あるいはその混合地帯に存在するものたちを無視すべきなのか? それとも、そこに飛び込んで、それこそがネット時代における新たなネイティブ・ランゲージなんだと認めるべきなのか?って」
う〜ん...創造活動が悪意にいつでもひっくり返ってしまうような危惧も...
何ごとも----それが「純な想い」か「悪意か」、「リスペクト」か「パクリ」かを分けるのは、AIの善し悪しではなく、それを扱う人間の精神性にあると感じます。
AIがどれだけ進化しても、その背後にある"眼差し"や"動機"がなにか?"目的"は?...
だからこそ、問われる時代、精神性の時代
創る側に敬意や愛があれば、AIとの共作にも光は差す。
The Velvet Sundownにも、そんな可能性の兆しが現時点で見えるようで、そこに私は惹かれているのかもしれません。
戒めも込めて----技術の問題ではなく、私たちの在り方=精神性が問われているのだと思います。
では、あらためてこちらを〜
近日中に3枚目がアップされるそうです。3枚目、どうなっているか?楽しみでもあります。