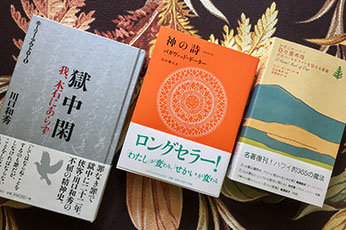MAGAZINEマガジン
農らいふ農てんき日和
田んぼの草刈り、始まる季節です
*TAO LABより
この時期、田んぼでは草刈り作業が本格化してきます。
Kさんは草刈り機に「アイガモン」というカッターを取り付けて作業されています。株と株の間が約40cmあり、このカッターのサイズにちょうど合うそうです。
ちなみに、今は「アイガモンⅡ」という新型も登場しており、お値段もかなりお手頃になっています。
稲の状態、植え方、その後の育て方〜お薬にドブドブの通常のお米の育て方に比べたらベターですが、中でも、アーティストであり友人の真砂秀朗さんは、耕さず、代かきも行わず、不耕起移植栽培というスタイルでお米を育てています。
その鍵のひとつが「冬期湛水(とうきたんすい)」という考え方。この夏はその取り組みについて、改めて深く学んでみたいと思っています。
ちなみに、8月3日には軽井沢で真砂さんのコンサートが開催されます。タオラボブックスも協賛していますので、ご興味ある方はぜひ。自然や音楽、そして田んぼの話まで、いろいろな気づきがある時間になると思います。
チケットはこちらからどうぞ。
作業効率がよく、なおかつ環境にも配慮できる目からウロコの方法がいろいろとあります。
とはいえ、食のスタイルと同じように、どのやり方が「ベスト」かは人によって異なります。田んぼのある土地の環境や、地域社会の状況によっても変わってきます。
まずは、自分の環境でできることから。池のまわりに広がる水田でも、可能な範囲で試してみるのもよいかもしれませんね。