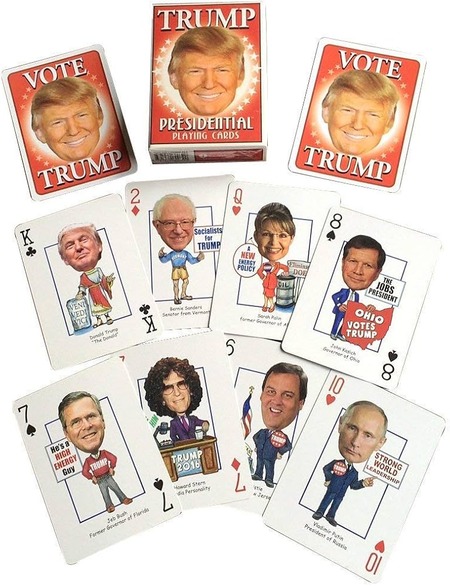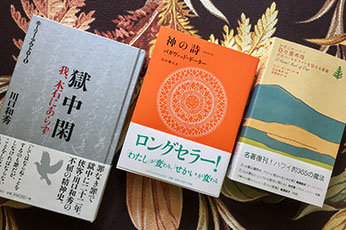MAGAZINEマガジン
三つ子の魂 by TKC
マイ・ルール
神出鬼没で多動性の白澤さんより、ご自身SNS投稿からインスピレーションを受け伝言ゲーム的な展開、またそこから抽出したTKC流の深堀りしてみたらと「楽しそう」なお誘いを受けて、SNSのみならず『TAO LAB』のその八面六臂で膨大なアーカイブにリンクしたヨモヤマ話も、手短か且つ手前勝手にやらせていただけたら幸いです。
さて、「トランプ」が私は大好きです。
...というと驚かれるご時世だと思いますが、大統領でなくカードゲームの方です。
「神経衰弱」から果ては「コントラクト・ブリッジ」(二組)まで同じ四種×13枚のカードなのに世界各国で様々な「ルール」によって大人から子供まで時間を忘れて楽しめるアイテムです。
日本では「花札」「双六」に代表される「ランダム」性を面白がる「遊び」の伝統がありますが、昭和40年頃の日本に移住したアメリカ人作家が中国経由の「囲碁」「将棋」や日本発「人生ゲーム」「オセロ」等のタカラ、トミー、エポックのボードゲームに触発され影響し合った作品群を発表しました。
そのうねりがいつしかドイツで花開き多くの作家により深化され、かのキース・リチャーズも家族と楽しんだ「カタン」に代表される数々の名作が生み出されています。「ゲーム」には人々を楽しませ、ジレンマに陥らせ、ギャンブルとなれば人生をも終わらせてしまうほどの魔力があり、その「ルール」を編み出す作家は魔法使いとでも言える存在だと思います。
ゲーム理論という「ロジック」の学問があるようですが、四象限マトリクスで分析(突き詰めれば対比 = 科学)する傾向にあるらしく触手が延びません。以下に自分がゲームを楽しくすると思える六つのエレメントを無責任に挙げてみます。敢えて説明は省きます言葉から想像して下されば嬉しいです。
カウンティング
バッテイング
オークション
アビリティ
バースト
ブラフ
トランプさんの「ディール」は丁と出るか?半と出るか?「さあ、張った張った!」
*本日の三コマ
今回は、旅のお供に一生遊べて携帯出来るカードゲームのド「定番」をチョイス。

①「ハゲタカの餌食」
上の文章で紹介したアメリカ人作家アレックス・ランドルフの作品。得点カードをオークションする要素と刀で切りあうようなバッテイング要素でテンポよく場が展開する。さらにマイナス得点カードがピリリと辛いジレンマを誘い思わず繰り返し遊んでしまう。運の要素だけの「ウノ」より数段深い味わい。

②「ごきぶりポーカー」
ランドルフに影響を受けたドイツ人作家ジャック・ゼメの作品。害虫や害獣カードを押し付けあうブラフ要素満載の「ダウト」進化版とも言えるコミュニケーションゲーム。落とす相手をパスで連携してバーストさせたり色々性格が表れる。伊集院光がハマりドイツゲームが次々紹介されるきっかけとなった。

③「ラブレター」
ドイツの巨匠ライナー・クニッツァも舌を巻いた日本人作家カナイ・セイジの作品。たった16枚のアビリティカードの効果を駆使して最後までサバイバルするゲーム。カウンティング要素のおかげで読みあい合戦となり、何度遊んでも新しい展開や戦術を楽しめる。日本のミニマリズムの結晶と称される作品。