MAGAZINEマガジン
平凡な覚醒 by しろかげ。
ガラスの繭 エピローグ
「母さん、これどう見たってネズミよね。たしかお父さんってばモグちゃんって呼んでいたけど」
「あら、書斎にあったのかい?小さい頃からの宝物だと言っていたからねぇ」
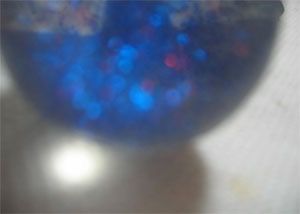
父の葬儀が終えて、この部屋からは永遠に主人がいなくなってしまったけれど、三方の壁に聳え立つ書架から立ち込める湿度を帯びた本の匂いも、月が蒼く射し込む大きな窓も、昨日までと全く変わりなく、同じ律動で呼吸していた。
ひとまず当面はそのままにしておこうと母と相談しながら、それでも雑多なものは整理しなくてはと抽斗を開いて、私はそのくたびれきった小さなぬいぐるみと目を合わせたのだった。
「なんだか秘密のポケットがあるんだと言っていたよ」
「ふーん...」
そう言えば私もそんな話を幼い頃に聞かされたことがある。もはや全身の毛が磨耗して辛うじて輪郭が保たれているだけの見窄らしいネズミのぬいぐるみを、あの処分好きの父がよくも捨てずに取り置いていたものだ。
「たしか背中にファスナーが着いてるのよね。これのことなのかなぁ?」
そのポケットは、子どもの指でも2本でいっぱいになってしまうほどのちっぽけな空間で、全くもって用途が不明なつくりになっており、父は幼い日の私が訝しんで乱暴に扱うことを予期していたのだろう、決してネズミを私の自由にさせることはなく、私には秘密の場所に安置していたのだった。
「お父さんの石、ちょうどぴったり納まりそうだけど、そんなこと言ったら不謹慎かな」
データ葬でガラス化された父は、小指の先ほどのチップになって帰ってきていた。母を元気づけるための私の冗談に母は返答をしなかったけれど、私の手からネズミを受け取ると、その子がこれ以上ほころんでしまわないようにそっと抱いて、父のお厨子に丁寧に捧げた。香を焚くための火に照らされた父の石は、心なしか青く滲むように光って、母はそれを遠い日を確かめるように、火が終わるまでじっと見つめていた。
つづく>>>
しろかげ。>>>


